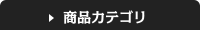本物のおいしい鰹節を届ける鰹節屋
「鰹節を見れば、産地や加工技術、腕がよけりゃつくってる人もわかるよ」
と威勢よく話すのは、鰹節を知り抜いた鰹節のプロ、「タイコウ」の稲葉泰三さん。
鰹節問屋は江戸時代から日本橋小舟町に軒を連ねていましたが、
現在は鰹節業者の多くが、中央区晴海にある鰹節センターに集まっています。
タイコウもそのひとつ。稲葉さんは荷受問屋だった父の仕事を引き継いだあと、
自分のやり方で本当においしい鰹節を、
乾物屋やスーパー、百貨店などの小売店に届けています。
タイコウで扱う鰹節は、すべて鹿児島県枕崎市のひとりの生産者がつくるもの。
しかも一本釣り漁法の鰹のみを使っています。
「なんで一本釣りかって、それがいちばんおいしいから。
おいしいものを売りたいというのがオレと誠さんの思いだからさ」
誠さんというのは、稲葉さんが全幅の信頼をおく、生産者の宮下誠さん。
枕崎産ということが大事なのではなく、
宮下さんがつくるものだからおいしいのだと稲葉さんは話します。

生産者との強い信頼関係があるからいい鰹節を届けることができるという稲葉泰三さん(左)と、生産者の宮下誠さん(右)。
現在主流である巻き網漁でとれた鰹は、網の中で暴れるため乳酸が多くなり、
味の質も落ちてしまいます。
一本釣りは漁獲高は少ないですが、鰹の損傷が少なく品質も最上。
そのほとんどは鮮魚用ですが、一部を確保してつくられるのがタイコウの鰹節なのです。
鰹節ができるまでは非常に長い工程があり、実に約6か月の月日がかかります。
いったん冷凍された鰹を解凍して3枚におろし、
「煮熟(しゃじゅく)」とよばれる工程で、沸騰させずに2時間煮ます。
冷めたら骨を抜き、あいた穴やへこみに中落ちのすり身をすり込んで修繕。
それから薪を焚いて鰹の水分をとる「焙乾(ばいかん)」という作業と、
火入れを休ませる「あん蒸(あんじょう)」という工程を繰り返し、
小さい鰹でも2週間、大きいものであれば2か月ほどかけて乾燥させます。
次に焙乾によって表面についたタールを丁寧に削り取り、天日干し。
その後、約3か月にわたるカビ付けが始まります。
カビは生育に必要な水分を鰹節から吸い上げて鰹節を乾燥させ、
ほかの雑菌の付着を防いで保存性を高めるのです。
さらに節に含まれる脂肪を分解し、必須アミノ酸を含んだたんぱく質に変化させます。
このカビのついたものが「枯節(かれぶし)」とよばれる鰹節なのです。
ムロと呼ばれるカビ付け室に入れ、1番カビがのるのに約2週間。
その後、天日干しをして再びムロに入れ、2番カビを乗せます。
こうしてじっくりと鰹節特有の香りとうま味が形成されていきます。
これらの工程を経てタイコウにやってきた鰹節は、
さらに日干と選別を繰り返し、商品になっていくのです。

タイコウの作業場に入ると鰹節のいい香りが。選別し、削り節などの加工も行います。